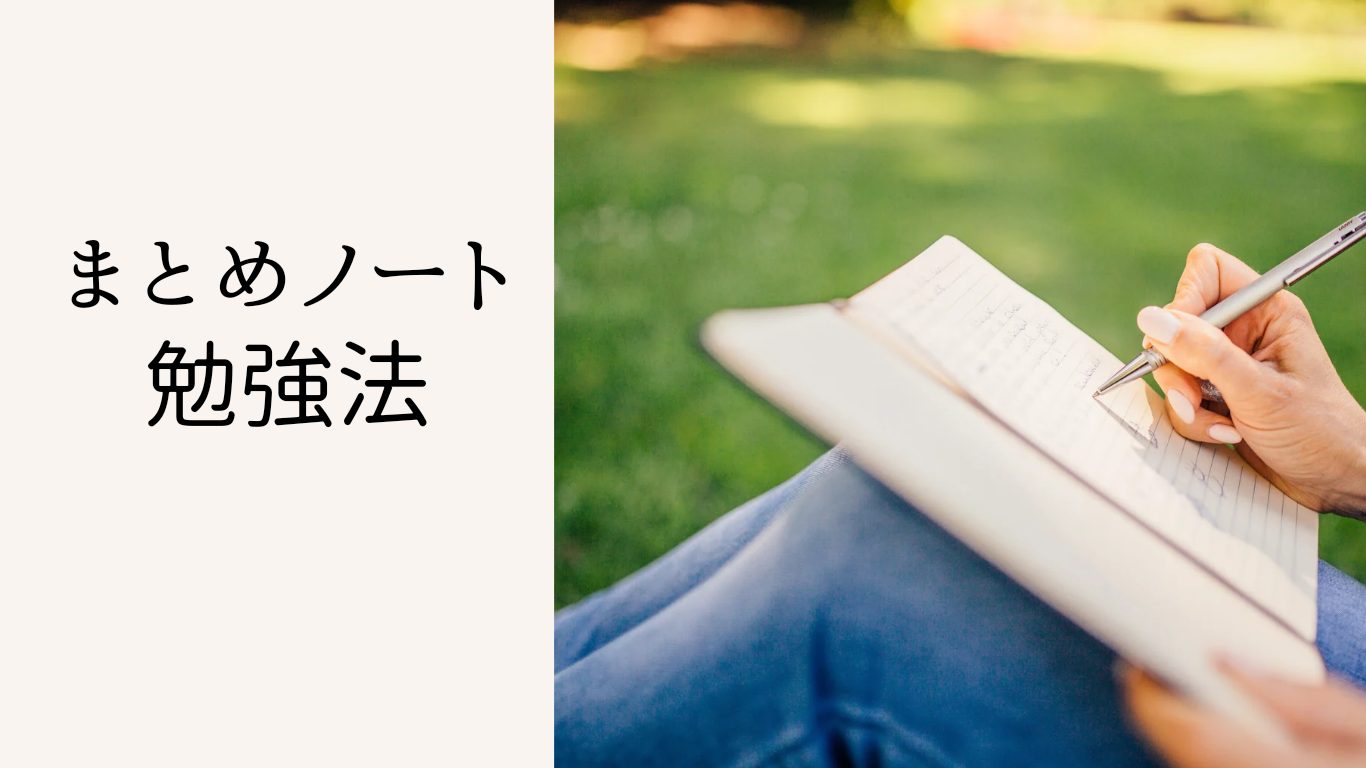効率良い勉強方法を知れたら良いですよね?
その方法が生徒に合う方法だったら良いですね。勉強をするからには効果を実感したいところです。
勉強の成果は中学生や高校生ではテストの点数になることが多いです。
「成績が上がることで、やる気が上がる!」効果も期待できますね。
学生の勉強一番頑張るときは受験です。
中学受験・高校受験・大学受験と各受験生にとっては、人生の選択肢が変わる機会になります。
受験はどの学校に進学しても不正解ではありませんが、せっかく受験勉強ができるタイミングで勉強のやり方がわかれば、これから先に勉強するときにも使える方法になります。
「社会は覚えるだけだから」「暗記教科だから」と言われることの多い社会の勉強について、効果の高い勉強の方法を紹介します。
社会のまとめノート術

社会科目の効率が良い勉強とは
効果の高い勉強の方法はアウトプットすることです。勉強のアウトプットとは問題を解くことになります。
たくさんの問題を解くことが結果を出す勉強する上では必須なことです。
社会科目では、歴史・地理・公民と単元が分かれていて、ぱっと思いつく勉強では教科書を読み覚えるとなりがちです。
ですが、教科書をただ読むだけでは覚えるのは難しいですね。教科書を読むと眠くなってしまうことも多いと思います。
次に思いつくのは教科書の内容をノートに書くことを考えることもありそうです。でも、実は効率の良くない方法の代表例だったりもします。
効率が悪い勉強の例
よくある効率の悪い勉強の失敗は、ほとんどが問題を解かないことです。問題を解かないで、教科書に書いてあることをなぞってしまうと失敗することが増えてしまい、せっかく勉強しているのに成果にならないことがあります。
- 教科書に書いてあることをノートに写す。
- 教科書をただ眺めているだけになっている。
- 教科書読んで、マーカーを引く。
- 授業を受けているだけで問題を解いていない。
社会を勉強するときの「やり方」
勉強の仕方として、テキストを「完璧になるまで繰り返す」が基本的な方法です。
社会の特有な勉強の仕方としては
- 「教科書を読む」
- 「単語カードを作る」
- 「まとめノートを作る」
- 「年表ノートを作る」
実は、これらの方法は効率が悪い方法の可能性が高いです。
まとめる勉強が効果が低くなりやすい理由
社会を勉強するときに【まとめノートを作る】【教科書にマーカーを引く】をすることは、効率が悪い場合があります。
教科書に書いてあることを他に写す作業になっている可能性が高いからです。
問題を解くことが勉強のやり方の基本に比べると、写す作業は覚えにくくなります。
まとめノートを作ることも良いことがある!
ここまで【まとめノート】は効率が良くない勉強方法というようなお話をしてきました。
生徒の勉強の様子を見ていると、まとめノートを作るのにも良いことがあります。
- 勉強したという達成感が得られやすい
- 勉強を始めやすい
- ノートに書いた量がわかりやすい
勉強を継続する方法でも書きましたが、勉強を続けるには「これだけやった」という記録が残ることは必要です。
勉強スタートというタイミングでは、なるべくハードルが低いことから始めることで「まずは0を1にする」ことも必要なことです。
ノートに書いた量でのわかりやすさがあるから、学校の宿題などでも出しやすいですね。「〇〇ページ以上書いたらA評価」とかの指標にも最適です。
こういったメリットもあるから、効率の良くない勉強方法を全て悪いとする必要はありません。
単純な効率だけを考えたら、問題を解くことです。同じテキストを使って覚えるまで繰り返し解くが効率は良いです。
効率の良いまとめノートでの勉強とは
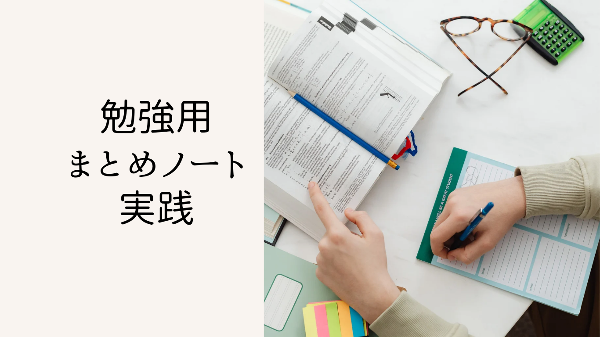
やっぱり、「まとめノートで勉強をしたい!」という方へ
ちょっとした工夫で効率良く学べる方法に変わる方法をお伝えします。
考えてみると「なぜ効果が出にくいのか」は、写しているだけになるからです。
それを少し変えてみましょう。ステップとして
覚えるためのまとめノート術を具体的なステップで紹介
そのときは見開き1ページくらいが良いです。その理由は教科者は見開き1ページで、ある程度完結している場合が多いからです。
ステップ1で教科書を読んだら、一旦教科書を閉じます。ここで重要ポイントは読んだ教科書に書いてあったことを思い出してみましょう。ちょっと目を閉じて瞑想する感じは良いですよ!
さあ!いよいよノートまとめです。ステップ1で教科書に書いてあったことを振り返りましょう!
何が書いてあったかを思い出すことが一番の目的です。書き方は文章よりも、図や表などを意識しながら先生になったつもりで、人に説明できるような書き方ができると良いです。
一旦、教科書を閉じるだけで途端に難しくなります。ステップ3で思い出しながらノートに書いてみたと思いますが、きっと書けなかったことも多いはず。どのようなことが書いてあったかを思い出した後で、教科書を読むことで必要なことを定着しやすくなります!
アウトプットとは、「思い出す」という作業
このときに大切なポイントはノートに書くときに教科書を閉じるということです。
思い出すためには目の前にあることでは思い出すにならないです。
教科書を閉じることで「なにが書いてあったかな?」と考えることにつながります。
是非、ノートに教科書の内容を書くことを勉強内容とするときには参考にしてください。