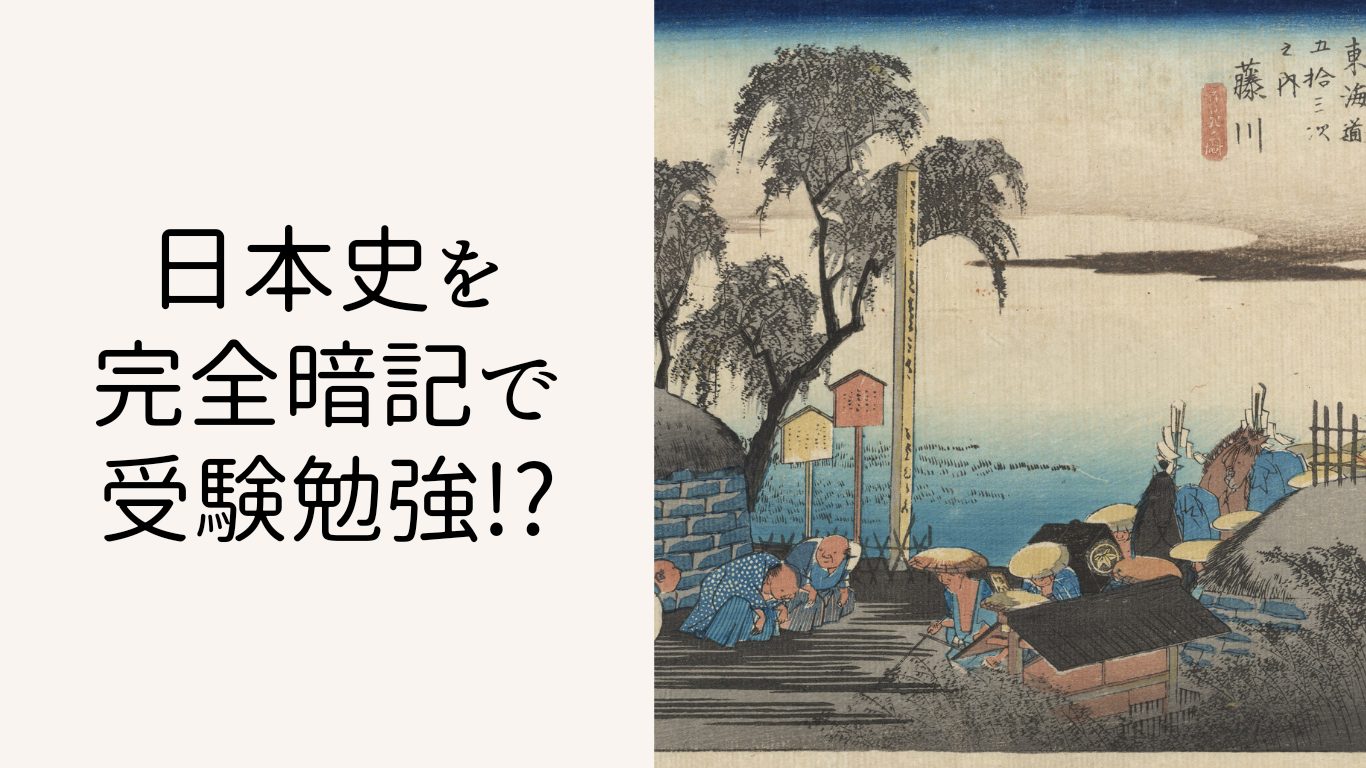社会という科目には、どのようなイメージがありますか?
中学生・高校生で社会を完全に暗記科目だと思っている生徒も多いです。
「社会は暗記だから」
「覚えるだけだから、直前でも良い」
「一問一答をたくさん覚えないといけない」
などと思われることが多い教科です。
ですが、年号と出来事を暗記するだけの科目が社会ではありません。
社会の勉強は覚えるだけ?
【社会は暗記するもの】と印象があります。社会を学ぶことは覚えるだけでしょうか。社会の勉強は中学生以降で悩む場合が増えてきます。
中学生からは社会も含めて定期テスト対策をする必要があるからです。小学生のうちは範囲が狭かったテストも中学生以降のテストでは、範囲も広くなるので対策が大変になってきます。
中学生、高校生だと社会は
中学生だと社会という教科になります。社会で学ぶ中では、歴史・地理・公民と分かれます。
高校生だと日本史・世界史・地理・現代社会・政治経済などと細分化されます。
教科名で社会と一括に考えても覚えることの多い科目です。例えば、
- 人物名が出てきたり
- 戦争の名前が出てきたり
- 法律の名前が出てきたり
- 年号が出てきたり
- 絵の名前や仏像が出てきたり
- 地名が出てきたり
があります。
覚えることは大切ですし、全く覚えてなくて乗り越えられる科目ではありません。
社会で覚えることとは
社会を暗記だけした結果
暗記だけで社会を乗り越えようとした生徒がいました。
大学受験生で日本史を選択した子です。
通塾前から日本史の勉強を頑張っていたと話を聞いていました。
使っていた教材は日本史の一問一答のみ
ただ、繰り返していてボロボロになるくらい使っていました。
ですが、日本史のことを雑談程度に話をした結果では
鎌倉時代の次の時代がわからない。
ということが発覚しました。
細かい出来事は暗記しているけど、歴史が「次にどうなったか」については本当にわからなかったのです。
社会を暗記だけでなくすには
社会は暗記と思いやすい科目です。
実際に覚えることが多いのは事実です。
ですが、一問一答の暗記だけで乗り越えることができるかというと無理です。
特に最近の入試傾向では共通テストも高校入試問題も、考える力を重視するようになってきました。
その結果、言葉を答えるだけの問題から読み取りが必要だったり推測して答えるような問題が出てくるようになりました。
だから、社会を勉強するときには
流れを重視するようにしましょう。
ただ流れと言ってもなにをすれば良い分からないと思います。
- なんで出来事が起こったのか
- この出来事が起こって変わったことは
- 出来事が起こって、得した人・損した人がいるのか
- 出来事の関係者はどう思うか
をイメージしながら勉強してみましょう。
ビオスタディでは
個別指導塾ビオスタディでは、授業・自習の中でも「考えること」も大切なことだと考えて教育をします。
ただの知識ではなく、考えた結果の知識になることで別の聞き方でも答えられる知識になります。
社会を学ぶ上で、例えば登場人物の気持ちになることで正解が導き出せるようになります。
どう思うかを考えることができると、他の出来事にも対応ができるようになります。
そして、勉強の仕方を学ぶことで社会科目以外でも同様の勉強方法で学ぶことができるようになります。